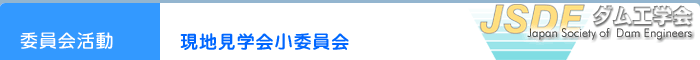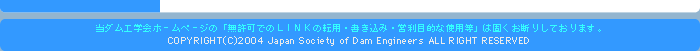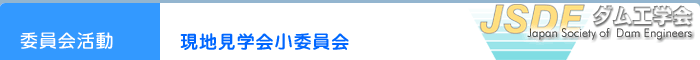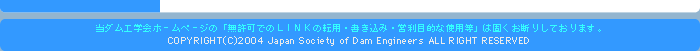|
|
現地見学会 案内
ダム工学会 第31回ダム現地見学会
見学するダムの概要
<高瀬ダム>
|
高瀬川は水量が豊富で急流河川であることから、早くから水力発電の適地として着目され、大正時代には高瀬川発電所が建設されていた。1969年から高瀬川に高瀬ダムを上池、七倉ダムを下池とした落差230mを利用した揚水式発電所・新高瀬川発電所(最大出力 1,270,000kw/h)の建設に着手し、1979年に事業が完成した。
高瀬ダムは型式はロックフィルダムであり、ダム高が176mと日本のダムの中では黒部ダムの186mに次ぐ高さで、日本屈指の巨大ダムである。
参考文献:第4回ダム施工技術講習会(1978.11.29)、ダム日本(737)
電力土木(307)、大ダム(93、96、100、115130、139)
曽野綾子『湖水誕生(上・下)』中央公論社1985 |
<七倉ダム>
|
七倉ダムは、高瀬ダムと同じくロックフィルダムで、ダム高は128mで高瀬ダムより1年早い1978年に完成している。七倉ダムは揚水発電の下池としての役割の他、下流に1985年に完成した大町ダムを逆調整池として効率的な発電運用を行っている。
参考文献:ダム日本(737)、ダム技術(208) |
<大町ダム>
|
大町ダムは、型式が重力式コンクリートダムで、ダム高は107mで1985年に完成した。目的は、水量が豊富で急流河川の高瀬川の洪水調節の他、不特定利水(冬季における青木湖・木崎湖の水位維持など)、長野市・大町市への上水道供給、七倉ダムの逆調整を兼ねた発電としている。
参考文献:ダム日本(441、453、479、499、507、508、513、737)、
ダム技術(4、181、208)、大ダム(110) |
<関電トンネル>(施工 熊谷組)
|
黒部ダム建設工事に使われるセメント、鉄材、工事用機械や鉄管、水車、発電機などの輸送のため、アルプスの山腹を貫通させる関電トンネル(延長5.4km、幅員5.0~6.4m)が昭和31年6月に着工したが、1957年5月1日坑口から2,600mの地点で大破砕帯に遭遇した。この大破砕帯の延長は82m、全湧水量は4,800,000m3、(660リットル/秒)水圧は42kgf/cm2でトンネル内は脛までつかる4℃の冷水に浸され、坑内の気温は7℃であった。この大破砕帯を突破するのに約7ヶ月を要し、1958年2月25日に、間組が黒部側から掘っていた導坑と貫通した。
(木本正次著『黒部の太陽』(信濃毎日新聞社)より) |
<黒部ダム>
|
建設当時(1956年8月着工)アーチダムとしては世界第1位のTignesダム(1952年、高さ182m、仏)を凌ぐ大きさの黒部ダム(高さ186m)を建設することは、プロジェクトの規模や技術的・経済的条件からも当時の常識を遙かに超える大型工事であった。当時、急激な電力需要の伸びに対し、電源構成は水主火従から火主水従へと変わる時代で、ピーク需要を賄うための大貯水池式発電所の必要性が強く求められ、黒部川第四水力発電所建設が敢行された。過酷な条件下の苦闘により、1963年6月(営業運転1961年1月)に完成した。
ダムの形状は、当初は通常のアーチ式ダムであったが、工事の進捗に伴う地質調査などからアバットメントの調整、ウイングダムの設置など大規模な設計変更を行っている。
参考文献:ダム日本(719)、ダム技術(174、200)、
大ダム(112、154、175)、電力土木(223、233、275) |
<黒四発電所>(施工 大成建設)
|
発電所: |
地下式 鉄筋コンクリート造り、壁・天井 二重構造(湧水処理のため)
大きさ 幅22m、高さ33m、長さ117m、水車中心標高 858.5m、最大出力 335,000kw/h |
| |
|
|
開閉所: |
地下式(L字型、変電所の上階)、鉄筋コンクリート造り
大きさ 幅20m、高さ13.6m、長さ182m |
| |
|
|
変電所: |
地下式(L字型)、鉄筋コンクリート造り
大きさ 幅20m、高さ13m、長さ149m |
<仙人谷ダム>(関西電力上部軌道車中より見学)
|
関西電力仙人谷ダム(事業者は日本電力㈱→日本発送電㈱→関西電力㈱、施工者は佐藤工業㈱)は1940年に完成した高さ43.5mの重力式コンクリートダムである。水は下流の欅平にある黒部川第3発電所(出力81,000kw/h)と新黒部川第3発電所(出力105,000kw/h)に送水されている。現在の黒三発電所は1973年に無人化され、関西電力㈱新愛本制御所(宇奈月町)から遠隔操作されている。
仙人谷ダムを建設するには、欅平から専用敷道を6km延長する必要があった。そのため欅平の山中に200mの縦坑を掘り、トロッコの乗るエレベーターを設置して、その上部地点から仙人谷ダムサイトまで上部軌道で結ぶ資材運搬ルートを確保した。上部軌道の隧道は高熱のため、黒部川の冷水を汲み上げ、切羽の坑夫にホースでかけて体を冷やし、高熱隧道作業は1日1時間作業(切羽は20分交代で1日3回)で行われた。賃金は破格であったが、作業員は熱射病、胃腸病の障害に悩まされ、カルシゥム注射や栄養補給(当時では貴重な卵、牛乳)の措置がとられた。
切羽の温度は火薬の使用制限の3倍の120℃まで上がり、ダイナマイトを断熱材(エボナイトや竹)の円筒にくるんで装填するなど、不可能を可能とするため想像を絶する挑戦が行われた。
この高熱随道工事を小説化した吉村昭の『高熱随道』(新潮文庫・昭和50年)がある。
また、この工事では、事故や雪崩により多数の犠牲者が出た。特に1938年12月27日の午前2時の志合谷泡雪崩は強烈な突風を伴って鉄筋コンクリート4階建て半地下式の宿舎を襲い、2階以上を人間もろとも谷の対岸まで吹き飛ばした。
(インターネットより抜粋) |
<小屋平ダム>(黒部峡谷鉄道車中より見学)
|
関西電力小屋平ダム(事業者は日本電力㈱→日本発送電㈱→関西電力㈱、施工者は㈱大林組)は昭和11年に完成した重力式コンクリートダムである。水は下流の猫又にある黒部川第2発電所(出力72,000kw/h)、新黒部川第2発電所(出力74,200kw/h)に送水されている。ダムの側には関西電力の資材置き場が設けられている。ダムの形状は、仙人谷ダムとほぼ同じ形状である。
(インターネットより抜粋) |
<出し平ダム>
|
関西電力出し平ダムは1985年に完成した重力式コンクリートダムである。水は下流の音沢発電所(出力124,000kw/h)、新柳河原発電所(出力41,200kw/h)に送水されている。このダムの特徴は、急流である黒部川の堆積土砂を下流の宇奈月ダムと連携して排砂するために、日本で最初の排砂ゲートを備えている。1985年に完成して6年後の1991年から排砂を実施している。
(インターネットより抜粋)
参考文献:ダム日本(481)、ダム技術(123、190、207、210)、大ダム(108、116、152、162)、電力土木(198、286、305)、ダム工学(39、46) |
<宇奈月ダム>
|
国土交通省の宇奈月ダムは黒部峡谷では最も新しいダムで洪水防止や発電(関西電力宇奈月発電所出力20,000kw/h)などを目的とした多目的の重力式コンクリートダムで1991年に完成した。このダムの特徴は、上流の出し平と連携して排砂するために排砂ゲートを備えていることである。
参考文献:ダム日本(547、584、609、639、666)、ダム技術(132、142、150、176、190、202,207、210)、大ダム(138、177)、電力土木(273、305)、ダム工学(39) |
|
(注)高瀬ダム、七倉ダム、大町ダム、黒部ダム、黒四発電所、仙人谷ダム、小屋平ダム、宇奈月ダムについては、参考文献の他にインターネットでも検索できます。関電トンネルの破砕帯などについて小説化した木本正次著の『黒部の太陽』(毎日新聞社)をご覧下さい。 |
|